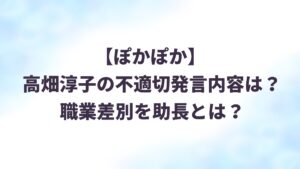最近耳にする機会の増えた、「子持ち様」という言葉。その意味は「育児を理由に仕事を切り上げたり育休を取る同僚」を揶揄する言葉とのことです。
そこで、そもそも「子持ち様問題」が発生する理由はどこにあり、どうすれば状況の改善に繋げられるのかを整理してみました。
「子持ち様」問題について、状況を整理したい方は是非ご覧ください。
「明日休むんだって」子持ち様に対する不満
- 子持ち様が休みを取る、そのしわよせが誰に来てるか理解してる?
- 自分は子供いないのに、子育てしてる側ばっか優遇してどういうこと!
おそらく「子持ち様」に対する不満の根っこはこの2点。
それを「お互い様」で片づけられることへの憤り。
「子供を作らなかった人の老後負担を、子供を作った人の子供が負っている」と「お互い様」の理屈を振りかざしたところで、
・高まり続ける生涯未婚率=2020年で男性28.3%、女性17.8%(引用元:Yahooニュース)
この状況では、「だから?」と感じる人が多そうです。
一方、直面する業務カバーによって生じる仕事の負担増に対する不満。その不満が「子持ち様」という表現にまでに高まった原因はどこにあるのでしょう?
子持ち様問題 原因1(社会環境の変化)
原因の一つ目は社会環境の変化です。具体的には
子育て世帯の減少
2022年の厚生労働省の「国民生活基礎調査」によれば、18歳未満未婚の子供がいる子育て世帯の割合が初めて全世帯中20%を下回り18.3%、となり減少の一途をたどっています。
つまり、
- 「子育て世帯が今では少数派」
- 「子供を育てた経験のない大人」=「子育ての苦労がイメージ出来ない大人」が増えている
のが現代社会の特徴です。ちなみに子育ての苦労とは・・・
子持ち様の苦労(欠勤の理由)
- 子供の体調変化(コントロール不可)
個人差はあるが保育園・幼稚園での感染多い
病状(インフルエンザ、入院等)によって複数日の付添い療養が必要
もちろん夜間の緊急通院も発生 - 子供の行事(入園式等)参加
子供だけでの行事参加?事実上不可能
そもそも、子供の分家事が増え、言うことを聞くわけではない子供との関わりも大変、そのストレスは覚悟の上での子育て。
とは言え、この状況自体は20年前と比べて悪化しているわけではありません。
子育てと仕事の両立。その大変さは昔も今も大きく変わらないにも関わらず、「子持ち様」という言葉に代表される、子育てする側と独身者との間の顕著な分断。
社会環境の変化以外にも「分断」が進む理由はありそうです。
子持ち様問題 原因2(労働環境の変化)
原因の二つ目となるのが、労働環境の変化です。
働き方改革
2018年6月に成立した「働き方改革法案」、2019年4月から順次施工されている「働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)」。
いずれも労働力人口減少の避けられない日本が取り組む方向性として、「一億総活躍社会の実現に向けて」というスローガンのもと、労働参画人口(主に女性・高齢者)を増やし、労働生産性を高める目的で始まりました。
しかし、「時間外労働の上限規制導入」については今でも議論の対象となっています。
時間外労働の上限規制導入
この制度により大企業、中小企業関わらず、残業時間の管理、削減に大きく舵をきることになりました。実際に、優秀な社員採用が課題となる中小企業においても、残業時間の抑制は大きなテーマとなっています。
一方、資本面で対応余力の高い大企業ではテレワークをはじめとした合理化投資、DX投資、人員補充による対策を進め、多くの中小企業では残業抑制を従業員、管理者の工夫で乗り切らざるを得ないという格差も生まれています。
育児・介護休業法
育児に関係する育児・介護休業法も、女性労働力確保を目的とした「女性活躍社会推進」を背景とし順次改正が進み、時短勤務による育休復帰者が特に正社員では増えてきています。
更に看護休暇の制度的整備(第1子年5日)も進み、子供が病気になった場合の休業についても(5日が充分かはさておき)、養育者への配慮が進んでいます。
このように、女性の労働参画率を高める労働施策の変更も、結果として子育てする側と独身者との間に「分断」を生む原因となってしまっています。
それでは、現状をふまえどのような解決の方向性があるのでしょうか?
対策
現状整理
- 現場では労働環境のストレスが加速
- 育児しながらの就業環境は急速に改善
- 出生率の低下は依然として改善されず
少子化の改善が進まないなかでの「一億総活躍社会」実現。そこに無理があることは明白です。
「子育て様」ストレスを抱える独身者が、結婚したとして子供を持つことに前向きになれるでしょうか? 子育て支援のつけを払わされている、と感じさせたなら、これほど虚しいことはありません。
- 子育てをしている側も、権利を振りかざす意識があるわけでもなく本心は申し訳ないと感じている。
- しわよせが来がちな独身者も、本当であればそんな文句を言いたくない。
- (強いて言うなら)雇用側にも丸投げされた意識がある。
その意味では全員が被害者とも言えます。もちろん雇用側の責任逃れは許されませんが・・・
対策方向性
経営側の責任を論ずるばかりでは、救われない従業員が大量に発生するであろうことを考えると、今望まれているのは政府主導での「お互い様」という世界観からの脱却。
- しわ寄せを受けている従業員の金銭的補償
- 社会的子育て支援の拡充(子育て業務を切り分けし部分的に社会でサポート)
もちろん、雇用側は当然として、地域社会で対応可能な対策もまだまだあるはず。
そして、それこそが少子化対策には欠かせない施策ともなりそうですね。
最後に、政府が発表した2024年5月度で最新の助成制度についてご紹介をしておきます。政府も対策を急いでいるようです。
両立支援等助成金 (引用元:厚生労働省ホームページ)
・しわ寄せを受けている社員を中心とした補助制度(対企業)
まとめ
・「明日休むんだって」子持ち様に対する不満
無償で業務のしわ寄せを受ける独身者にとって、「お互い様」は無理筋
・子持ち様問題 原因1(社会環境の変化)
子育て世帯がどんどん少なくなる現状を無視した子育て支援は共感得にくい
・子持ち様問題 原因2(労働環境の変化)
現場に丸投げの「働き方改革」が、中小企業を中心に大きな歪みを生み、その一つが「子持ち様問題」
・対策
政府主導での「お互い様」世界観からの脱却こそが「子持ち様問題」を緩和し少子化対策となる、具体的には「しわ寄せを受けている従業員の金銭的補償」や「社会的子育て支援の拡充」など